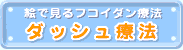|
|
||||||
|
|
|||||||
|
現在位置:ホーム > がん種別 フコイダン療法 > 肺がんとフコイダン療法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
フコイダンのアポトーシス誘導効果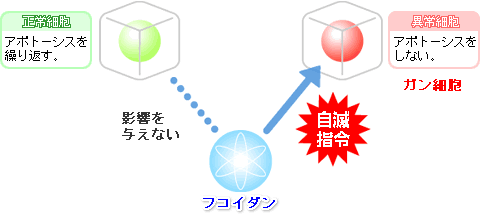
生物の細胞には異常環境で老化したときに「自滅するように、指令する遺伝子」が組み込まれており、この働きで細胞が自然死することを「アポトーシス」と言います。 抗がん剤と超低分子フコイダンの併用についてフコイダンと抗がん剤の併用をすすめる理由に、がん細胞の抗がん剤への耐性を抑制するというものがあります。 抗がん剤の種類分子標的薬肺がんの種類と経過▼小細胞肺がんと非小細胞がん小細胞肺がんは、肺がんの中でも最も進行が早く、悪性度が高いとされています。しかし、その反面、小細胞肺がんには、抗がん剤や放射線療法がよく効くという特性があります。これに対して、非小細胞肺がん(腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん)の場合、進行は緩やかなタイプが多いとされていますが、抗がん剤治療や放射線はあまり有効でないとされています。 癌の進行小細胞肺がんは「限局型」と「進展型」に分けられます。肺の入り口に近い太い気管支に多く発生するものが多く、気管支の壁を這うように進展します。また、早い時期からリンパ節や脳への転移が見られ、ほとんどの場合、進行がんの状態で発見されています。 肺がんの診断▼病理診断小細胞肺がんではほとんどの場合、気管支ファイバースコープによる気管支鏡検査によって、直接細胞を採取します。そして、得られた標本の病理組織検査によって、悪性の細胞や組織を証明することができます。非小細胞肺がん、特に腺がんは気管支鏡が入らない場所にできる事が多い為に針を使って細胞を採取して確認されます。 ▼病期診断通常行われる検査は、脳のCTやMRI検査、胸のCTやMRI、腹部のCTや超音波検査、骨シンチなどが行われます。また、CT検査ではより精度の高い診断のため、造影剤を入れて検査をします。さらに最近は、より精度の高いPET検査が、がんの診断及び病気の拡がりの診断に用いられることが多くなってきました。その他、一般の血液検査に加え、腫瘍マーカーと呼ばれるがん細胞によって産生される物質の検査も行います。一般的には、CEAを検査しますが、小細胞がんでは、NSEやProGRPの検査も行います。 肺がんの治療▼外科療法非小細胞肺がんに対する外科的療法は、リンパ節転移や遠隔転移の見られない1期から2期の患者に行われています。小細胞肺がんに対する外科的療法はほとんど行われていません。 ▼化学療法(抗がん剤)非小細胞がんに用いられる主な抗がん剤は、シスプラチン、カルボプラチン、ビノレルビン、イリノテカン、パクリタキセル、ドセタキセル、ゲムシタビン、ティーエスワン、ゲフィチニブなどです。小細胞がんに対しては、シスプラチン、カルボプラチン、エトポシド、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、イリノテカン、イフォマイド、などが用いられます。これらの抗がん剤は1種類で用いる場合もありますが、2種類以上の抗がん剤を組み合わせて用いる場合が標準治療とされています。 ▼放射線療法X線や他の高エネルギーの放射線を使ってがん細胞を殺す治療です。肺がんの場合、通常は身体の外から肺やリンパ節に放射線を照射します。非小細胞がんの場合は手術できないI期から3A期、胸水を認めない3B期、小細胞がんの場合は限局型が放射線治療の対象となります。また、小細胞がんは脳へ転移する場合が多く、脳へ転移するのを防ぐ目的で脳放射線治療が行われることがあります。 ▼非小細胞肺がん治療開始からの5年間生存する割合は、がんの病期と全身状態により異なります。手術をした場合の5年生存率は、病期I期70%、II期50%、IIIA期25%といわれています。手術が適応でないIII期で、放射線と抗がん剤の併用療法を受けた場合、2年生存率は40〜50%、5年生存率は15〜20%です。IV期で抗がん剤治療を受けた場合、1年生存率は50〜60%です。 ▼小細胞肺がん限局型で放射線療法と化学療法の併用療法を受けた場合、2年、3年、5年生存率はそれぞれ約50、30、25%です。進展型で化学療法を受けた場合、3年生存率は約10%です。 フコイダン療法関係リンク
|
|
■NPO法人統合医療推奨協会 所在地:〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田2-6-12 団体名:NPO法人統合医療推奨協会 /TEL:0120-258-050 フコイダン無料サンプル がん治療 |
||
| © 2004〜2008 Copyright NPO法人統合医療推奨協会 All Rights Reserved | ||